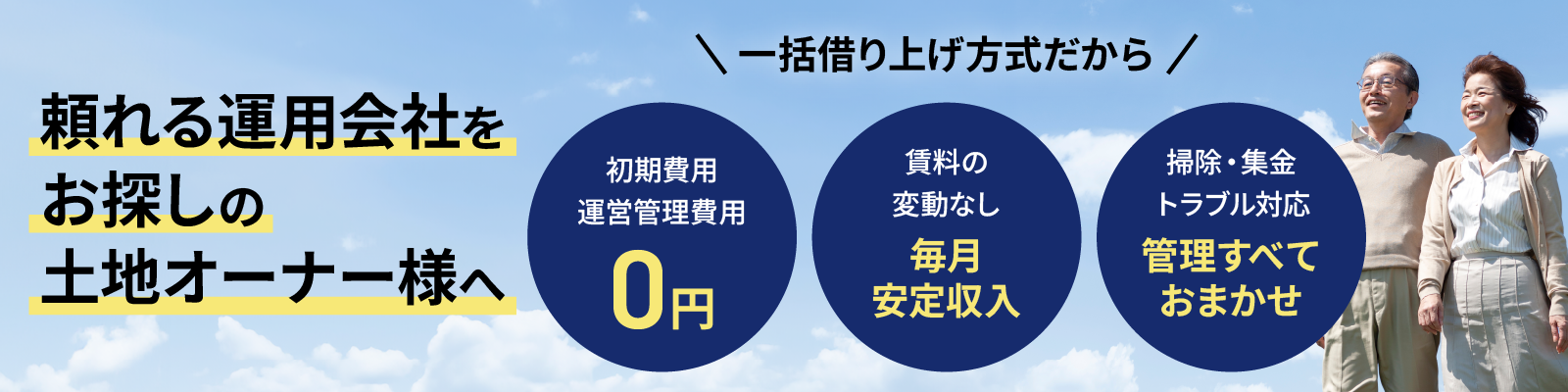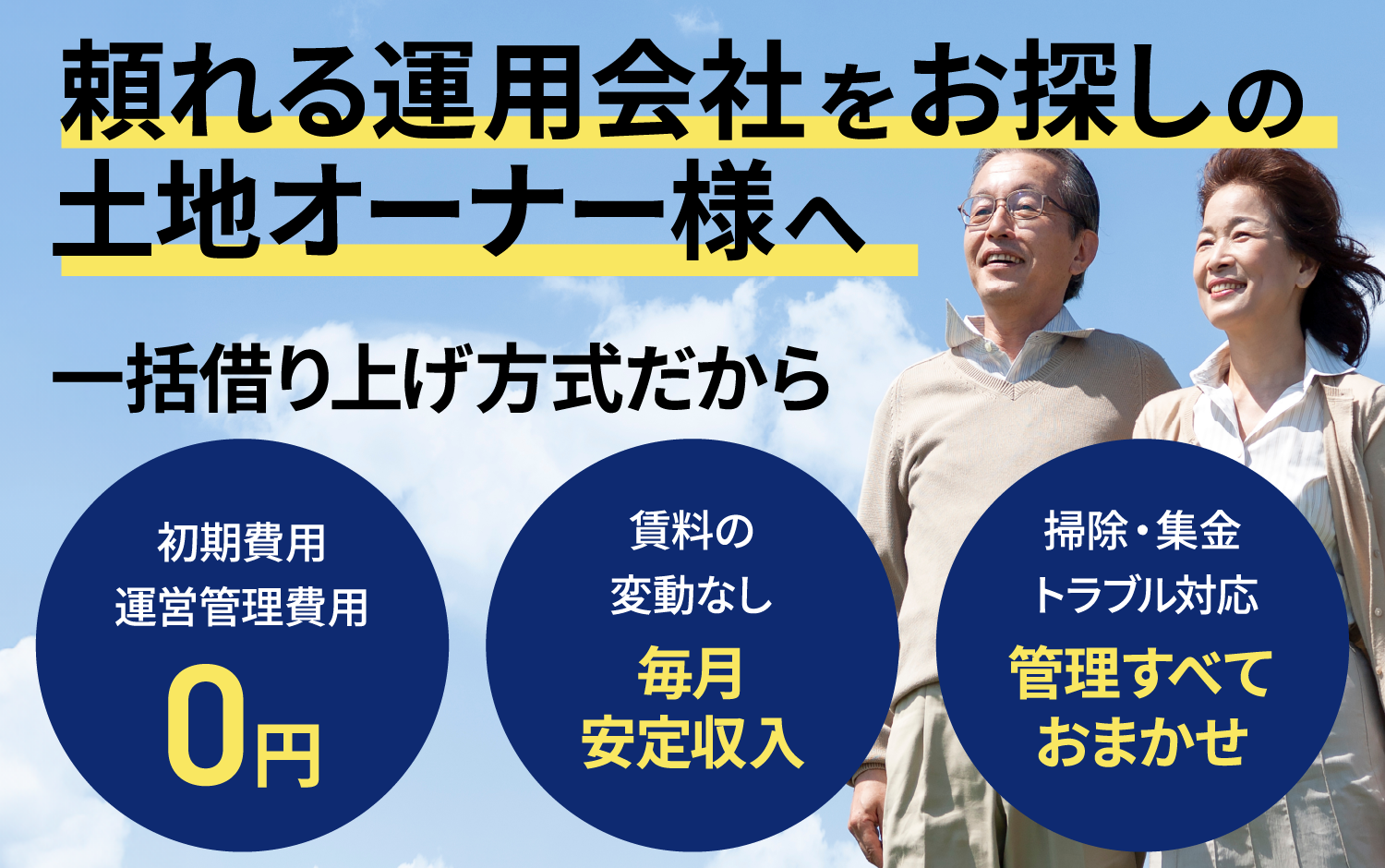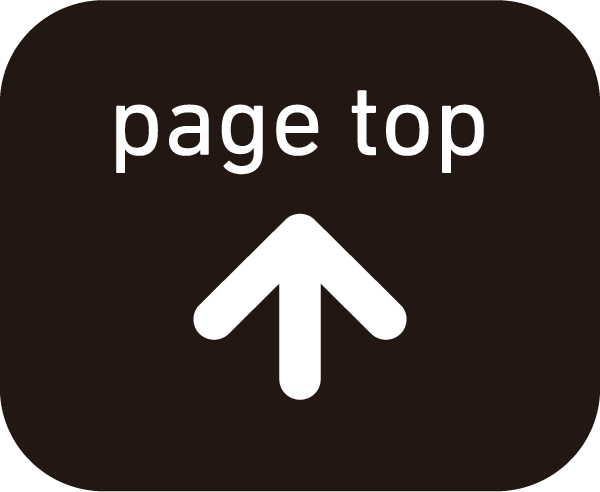親から土地を相続したり、今後相続の予定があるとき、まず頭を悩ませるのが「税金」です。
そんなときに注目したいのが【土地活用】。
うまく活用すれば、相続税評価額を下げられるうえ、毎月の収入も得られるため「節税」と「収益」の両方を実現できる可能性があります。
ただし、“相続前から準備しておく人”と“相続が起きてから慌てて対応する人”では、結果が大きく変わります。
本記事では、土地活用がどのように相続税対策につながるのか、基本知識から活用方法、具体的なシミュレーション、専門家の選び方まで分かりやすく解説します。
相続や税金に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

Contents
相続対策としての土地活用
「土地をそのまま持っているだけで税金が高くなる」──実は多くの方が気づいていない事実です。
相続税の計算は、更地か貸家かといった使い方で評価額が大きく変わります。
まずはその仕組みを押さえておきましょう。
なぜ土地活用が相続税対策につながるのか
土地は「更地」で持つよりも誰かに貸して活用している状態の方が「自由に使えない土地」と評価されます。
この制約がある分、相続税の計算で使われる評価額が下がる仕組みになっているのです。
例えば、更地ならそのままの評価額が課税対象になりますが、駐車場やアパートにして貸し出すと「貸家建付地」として扱われ、評価額が2~3割程度下がるケースもあります。
つまり、同じ土地でも活用しているかどうかで税額に大きな差が生まれるため、土地活用は相続税対策として非常に有効といえます。
更地のままだと税負担が増える
土地を更地のまま持ち続けると、税金の面で不利になることが多いです。
まず、固定資産税や都市計画税は「住宅が建っている土地」よりも負担が重くなります。
住宅用地には税額を軽減する特例が設けられていますが、更地には適用されないためです。
例えば、同じ200㎡の土地でも、住宅が建っていれば固定資産税が最大で6分の1まで軽減されるのに対し、更地のままだと満額で課税されます。
その結果、毎年の維持コストが数十万円単位で違ってくることもあります。
さらに、相続の際にも更地は評価額が高く算定されるため、相続税の負担が重くなりがちです。
せっかくの土地が“資産”ではなく“負担”になってしまわないよう、早めの対策が欠かせません。
「相続後に活用する人」と「相続前から準備する人」の違い
土地活用は「いつ始めるか」で結果が大きく変わります。
相続が発生してから慌てて活用しようとすると、相続税の申告・納付までの10か月以内に対応しなければなりません。
短期間で入居者を集めたり、駐車場の整備を進めたりするのは難しく、節税効果を十分に得られないケースも少なくありません。
一方、相続前から活用を始めておけば、土地の評価額を抑えつつ、相続発生時にはすでに安定した収入基盤を確保できます。
つまり、「相続後に活用する人」は手遅れになりやすく、「相続前から準備する人」は安心して資産を守れるという大きな違いがあります。

節税の基本知識を押さえる
相続や土地活用を考えるうえで欠かせないのが「税金の基礎知識」です。
相続税・固定資産税・所得税などの仕組みを知っておくことで、無駄な負担を避けられます。
ここでは節税の考え方を、できるだけ分かりやすく解説します。
相続税の仕組み
相続税は「相続した財産の評価額」に応じて課税されます。
現金はそのままの額面で評価されますが、土地や建物は「相続税評価額」という基準で算出され、実際の時価よりも低めに評価されることが多いです。
課税額は次の流れで計算されます。
- 相続財産の合計額を計算
(例:現金3,000万円+土地の評価額2,000万円=合計5,000万円) - 基礎控除を差し引く
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(相続人が2人なら 3,000万円+600万円×2=4,200万円) - 課税対象額に税率をかける
残りの800万円が課税対象となり、相続税率を適用して税額を計算
このように、土地の評価額を下げることができれば、課税対象額そのものを小さくできるため、結果として相続税の軽減につながります。
「節税になるケース」と「ならないケース」
土地活用は必ずしも節税対策になるわけではありません。
条件によって効果に差が出る点を理解しておくことが大切です。
節税になるケース
- ・更地を駐車場やアパートにして貸し出すと、土地の評価額が下がる
- ・アパートやマンションを建てると「貸家建付地」として土地の評価が抑えられる
- ・一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が使え、200㎡までの土地評価額が最大50%減額される
節税にならないケース
- ・更地のまま所有している場合(軽減措置がないため税負担が重い)
- ・活用を始めても空室が多く「貸している状態」と認められない場合
- ・要件を満たさず、「小規模宅地等の特例」が適用されない場合
土地活用が節税につながるかどうかは、「実際に貸している状態をつくれるか」 「税制上の条件を満たせるか」
この2つのポイントがカギとなります。
所得税も減らせる?不動産収入と損益通算の話
土地活用で得られる賃料収入は「不動産所得」として課税対象になります。
一見すると「収入が増えると税金も増えるのでは?」と思うかもしれませんが、実際には 経費を差し引いた後の利益に対して税金がかかります。
例えば、アパート経営なら次のような費用を経費として計上できます。
- ・修繕費や管理費
- ・固定資産税や都市計画税
- ・借入金の利息
これらを差し引くと、帳簿上の利益が小さくなり、所得税や住民税の負担を軽くできるケースがあります。
さらに、不動産所得が赤字になった場合には「損益通算」といって、給与所得など他の所得と相殺できる制度もあります。これにより所得税の還付を受けられることもあるのです。
ただし、節税ばかりに目を向けると「収益性が低い事業をわざわざ続けている」という本末転倒になりかねません。
土地活用では節税効果と収益性の両立を考えることが大切です。

土地活用の収益性を比較【駐車場・賃貸・トランクルーム】
駐車場経営の特徴
駐車場経営は、土地活用の中でも初期費用が少なく、比較的始めやすい方法です。
立地条件によって、コインパーキングか月極駐車場か活用方法が異なります。
※以下は、月極駐車場として運用した場合の例です
初期費用の目安
- ・区画整備や舗装を行う場合、5台規模なら70万円前後からスタート可能
- ・機械式のコインパーキングを導入すると数百万円かかりますが、月極駐車場なら整備コストを抑えられる
収益のイメージ
- ・月極駐車場の場合、地域によって差はありますが、1台あたり月1万円×5台=月5万円(年間60万円)
- ・利回りの目安は3〜6%とされ、他の土地活用に比べて堅実で低リスクな収益モデル
「投資回収が早い」こと、そして「狭い土地でも収益化できる」ことが駐車場経営の大きな魅力です。
大きな利益を狙うというよりも、安定した副収入を得たい方に適した方法といえます。
※記載のデータは自社調べによるものです
アパート・マンション経営の特徴
土地活用の中でも、規模が大きく収益性を高めやすいのがアパート・マンション経営です。
初期費用の目安
- ・建築費用は 数千万円〜1億円規模 になることも
- ・木造アパート:数千万円程度
- ・鉄筋コンクリート造のマンション:さらに高額
収益のイメージ
- ・満室経営ができれば、年間家賃収入は数百万円〜数千万円規模
- ・利回りの目安は 5〜8% とされ、駐車場より高い水準を狙える可能性あり
収益規模が大きい分、資産形成や老後の生活資金確保に効果的です。
一方で、初期投資が大きいため ローン活用が前提となり、長期的に運営して入居率を維持できる人に向いた形態といえます。
トランクルーム経営の特徴
住宅事情や収納ニーズの高まりを背景に、近年注目されているのがトランクルーム経営です。利用者は短期契約よりも長期利用が多く、比較的安定した稼働が期待できます。
初期費用の目安
- ・プレハブ型・コンテナ型:数百万円から始められ、アパートやマンションよりも少額で導入可能
- ・建物を新築するタイプ:数千万円規模になることもあり、高額投資が必要
収益のイメージ
- ・1室あたり月数千円〜1万円程度が相場
- ・利回りは 6〜10%程度とされ、安定的に稼働できれば駐車場以上の収益性を発揮するケースも
さらに、建物や設備に大きなメンテナンス費用がかからない点も、収益の安定要素です。
中規模の投資で「駐車場以上・賃貸未満」の収益を狙いたい方に適した土地活用といえるでしょう。

シミュレーションで見る土地活用の効果
「実際にどれくらいお金がかかって、どれくらい戻ってくるのか?」
気になる部分を数字でイメージできるよう、初期費用や収支例、節税額のイメージをシンプルに紹介します。
土地活用にかかる初期費用と収支の例
実際にどのくらいのお金がかかり、どのくらいの収益が見込めるのか。
ここでは代表的な土地活用のシミュレーション例を紹介します。
- ・駐車場(例:5台分・月極)
初期費用:約70万円(舗装・ライン引きなど)
収入:月5万円(1台1万円×5台)=年60万円
→ 維持費を差し引いても、1年半〜2年で初期費用を回収できます。 - ・アパート(木造2階建て・6世帯)
初期費用:約4,000万円
収入:月42万円(1戸7万円×6戸)=年504万円
→ ローン返済があるため、返済計画と空室リスク対策といった長期的な運営が前提。 - ・トランクルーム(コンテナ型20室)
初期費用:約1,500万円
収入:月16万円(1室8,000円×20室)=年192万円
→ 駐車場より高い収益を狙えるが、中規模の投資が必要。
このように、初期費用や運営内容は活用方法によって大きく変わります。
短期で元を取りたいなら駐車場、安定的な資産形成ならアパート、中規模で収益性を狙うならトランクルームといった選択肢が考えられます。
節税額のざっくりイメージ
土地活用は、収益を得られるだけでなく、相続税評価額を下げる効果もあります。
具体的な金額は土地の立地や活用方法によって異なりますが、イメージを持ちやすいように簡単な例をご紹介します。
- ・更地のままの場合
土地の評価額:5,000万円
→ 相続税の対象額もそのまま5,000万円 - ・アパートを建てて貸した場合
貸家建付地として評価されるため、評価額は5,000万円 → 約3,500万円に圧縮(▲30%程度)
→ 評価額が1,500万円下がり、相続税率30%なら450万円の節税効果 - ・月極駐車場として貸した場合
評価額は大きく下がりにくいが、実際に貸していれば一定の減額が認められるケースあり。評価額が5,000万円 → 4,500万円程度に(▲10%前後)
→ 評価額が500万円下がり、税率30%なら150万円の節税効果
このように、更地のまま持つか、貸して活用するかで 数百万円単位の差が出る可能性があります。
ただし「必ず節税できる」わけではなく、空室が多いと認められないケースや、特例の要件を満たさないと効果が得られないこともあります。
節税効果を狙うなら、必ず専門家にシミュレーションを依頼しましょう。
相続後すぐに現金が必要な人と、長期的に安定収入を得たい人
土地活用といっても、目的によって選ぶべき方法は変わります。
- ・相続後すぐに現金が必要なケース
相続税の納付は10か月以内に現金で行う必要があります。
そのため「納税資金を早く確保したい」「急ぎで維持費をまかないたい」という人には、駐車場や土地貸しといった短期間で収益化しやすい方法が向いています。
初期費用も少なく、運用開始までが早いのが特徴です。 - ・長期的に安定収入を得たいケース
一方で、「老後資金を作りたい」「長期で資産形成したい」と考えるなら、アパート・マンション経営のような形態が有力候補になります。
初期投資は大きいものの、家賃収入を長期的に得られ、節税効果も期待できます。
つまり、「すぐに現金が必要なのか」「将来に備えて安定収益を重視するのか」という目的の違いが、土地活用の選び方を大きく左右するのです。

失敗を防ぐための専門家活用法
土地活用と相続対策は専門知識が必要な分野です。
自己判断で進めると「思ったほど節税できなかった」「収支が赤字になった」といった失敗につながることも。
安心して進めるために、税理士・不動産会社・土地活用業者といった専門家の役割を押さえておきましょう。
税理士 ― 相続税や節税の専門アドバイス
土地活用を相続対策として考えるときに、まず頼るべき専門家が税理士です。
相続税は更地か貸家かといった土地の使い方によって評価額が大きく変わるため、正しいシミュレーションが欠かせません。
例えば、
- ・小規模宅地等の特例(最大50%の評価減)を使えるかどうか
- ・節税と「納税資金」をどう確保するかのシミュレーション
- ・将来の二次相続まで見据えた分割方法
といった点を分かりやすくアドバイスしてくれます。
「節税のつもりが後で否認された…」そんなリスクを避けるためにも、専門家に相談して進めることが安心への第一歩になります。
不動産会社 ― 収益性のシミュレーション
土地活用を考えるときに、もう一つ重要なのが「収益がどのくらい見込めるか」という試算です。ここは不動産会社の得意分野です。
例えば、
- ・周辺の家賃相場や入居率のデータ
- ・駐車場やトランクルームの需要調査
- ・将来の修繕費や管理費を含めた収支計画
といった数字をもとに、実際に利益が出るかどうかを具体的にシミュレーションしてくれます。
「建てたのに空室だらけ」「思ったより維持費がかかる」といった失敗は、収益性の見通しが甘かったケースがほとんどです。
不動産会社のデータと知見を取り入れることで、現実的な計画を立てやすくなります。
土地活用業者 ― 一括借上げで初期費用ゼロの選択肢
「土地活用をしたいけれど、初期費用が用意できない…」という方に有効なのが、土地活用業者による一括借上です。
例えば駐車場経営の場合、立地条件によっては舗装や精算機の設置といった整備費用を業者が負担し、オーナーは自己資金ゼロでスタートできます。
運営開始後は、業者が利用者からの料金回収やトラブル対応まで一括で担い、オーナーには毎月固定の賃料が支払われる仕組みです。
- ・自分で集客や管理をする必要がない
- ・空き区画があっても一定額の賃料が入る
- ・設備投資から日常管理までプロに任せられる安心感
こうした点から、「負担なく安定収入を得たい」「リスクを最小限に抑えたい」という方に特に向いた方法と言えます。
もちろん、契約条件によって取り分は変わるため、複数の業者から提案を受けて比較することが、より良い結果につながります。

土地活用で相続・節税・収益を両立する
最後に、土地活用を「節税」と「収益」の両面からどう考えるべきかをまとめます。
トラストパークの一括借上を活用すれば、土地活用を初期費用ゼロで始められ、安定した収益も確保可能です。
更地の“負担”から“資産”に変える
相続した土地を更地のまま持ち続けると、固定資産税などの税負担に加え、草刈りや清掃といった維持管理の手間がかかり、毎年「出ていく一方」の状態になりがちです。
さらに、更地は課税評価額がそのまま反映されやすいため、相続税の面でも不利になります。
一方で、駐車場やアパートなどに活用すると、土地は収入を生む「資産」として働きます。
貸家建付地として評価額が下がる可能性があるため、相続税の負担を軽減できるうえ、毎月の収益が家計の助けにもなります。
相続税対策と収益確保を同時に実現できる現実的な方法こそ、土地活用なのです。
節税と収益性のバランスを考えることが大切
土地活用は「節税」だけを目的にすると、思わぬ失敗につながりやすいものです。
駐車場やアパートとして運営すれば相続税評価額を下げられる可能性がありますが、空室や空車が続けば収入が減り、維持費や税金の支払いで赤字になるリスクもあります。
大切なのは、節税効果と実際の収益性をバランスよく見極めることです。
「節税で税額がいくら下がるか」だけでなく、「毎月どの程度の収入が見込めるか」「初期費用を何年で回収できるか」といった視点も合わせて確認する必要があります。
土地を活かすことで、税負担を抑えつつ安定した収益を得られるのが理想の形です。
そのためにも、節税と収益の両面からシミュレーションを行い、自分に合った方法を選ぶことが欠かせません。
トラストパークのサポートで安心経営
「土地をどう活用すればいいのか分からない」「初期費用をかけずに始めたい」──そんな方に向いているのが、トラストパークの一括借上げ方式です。
この仕組みでは、オーナーが土地をトラストパークに貸し出すだけで、コインパーキングとして運営するための土地の整備・設備投資・日常管理までをすべて代行。毎月の固定賃料がオーナーに支払われるため、空車リスクや管理の手間を負う必要がありません。
さらに、立地条件によっては初期費用ゼロでスタートできるケースもあります。例えば、舗装工事や精算機の設置費用をトラストパークが負担し、オーナーはリスクなく収益化を始められる仕組みです。
「税金ばかりかかる土地」を「安定収入を生む資産」へ──。
専門のノウハウを持つトラストパークに相談することで、安心して一歩を踏み出すことができます。
まとめ
相続した土地をそのままにしておくと、固定資産税や管理の手間ばかりが増え、相続税の面でも不利になりがちです。
土地活用をすることで、相続税評価額を下げられるだけでなく、毎月の収入源にもなります。
大切なのは、「節税」と「収益性」をバランスよく考えること。
相続直後に現金が必要なのか、将来の安定収入を重視するのか、自分の状況に合った活用法を選ぶことが欠かせません。
トラストパークなら、一括借上げによって初期費用ゼロで始められる仕組みや、安定収入を確保できるサポート体制が整っています。
「負担の土地」を「資産の土地」に変える第一歩として、専門家に相談しながら最適な活用方法を検討してみてください。